遺伝子解析、機能解析、臨床研究の3本柱で
悪性腫瘍における遺伝子異常の全体像の解明へ(前編)
片岡圭亮(国立がん研究センター研究所 分子腫瘍学分野 分野長)
2018.10.25

成人T細胞白血病/リンパ腫(ATL)におけるゲノム異常の全体像を網羅的に解析した研究を出発点に、ATLでは免疫チェックポイント分子の1つ、PD-L1の構造異常があることを突き止めた国立がん研究センター研究所の片岡圭亮氏。その後、他の悪性腫瘍でもPD-L1のゲノム異常があることを明らかにし、今後は、遺伝子解析、機能解析、臨床研究の3本柱ですべての悪性腫瘍に横断的にアプローチし、遺伝子異常の全体像の解明に挑んでいく。
2017年4月に、国立がん研究センター研究所分子腫瘍学分野の分野長の任に就かせていただきました。研究者としてのキャリアが10年足らずの私がPI(principle investigator)になったのは、多くの指導者や先輩のおかげであり、いろいろな後押しをしていただいたからだと感謝しています。そうした方々の期待に応えるべく、研究に取り組んでいます。
国立がん研究センターで本格的な研究を始めたのは2017年9月で、最初は私を含めて3人でのスタートでした。幸い、私の研究内容に共感してくれた研究者が集まり、現在は10人体制となっています。
研究の最初のテーマはATLのゲノム異常
約1年後にJSH、ASHでの口演発表に採択
私は2005年に東京大学医学部を卒業した後、2009年に大学院博士課程に進んでから、基礎研究に取り組むことになりました。はじめは造血器腫瘍についてマウスを用いた分子生物学的な研究が中心でした。2013年11月に京都大学大学院医学研究科腫瘍生物学講座に移り、ここで成人T細胞白血病/リンパ腫(ATL)のゲノム異常の研究を始めました。ここが、現在の私の研究の出発点と言えます。
ATLを研究テーマとした理由の一つは、ATLではこれまで網羅的な解析が行なわれていなかったことです。網羅的解析は、リンパ腫ではB細胞性腫瘍で進んでいましたが、4分の1以上を占めるT細胞性腫瘍については研究が進んでいませんでした。
ATLが特に日本で多いことも研究に取り組んだきっかけとなっています。現在、約100万人のキャリアがいて、年間約800〜1,000人が新規に発症しており、わが国で病態解明を進める意義は大きいと考えました。また、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)によってがん化するメカニズムにも興味を持ちました。レトロウイルスにより腫瘍が発生するのは、HTLV-1によるATLだけだからです。
研究内容は、ATL患者約400例の検体を用いて、全エクソン解析、RNAシーケンス、全ゲノム解析、SNPアレイによるコピー数解析、標的シーケンスによる変異の確認を組み合わせ、ATLのゲノム異常を網羅的に解析するというものです。400例の解析には、かなりの時間と体力を要しました。研究が本格化したのは2014年2月からでした。幸いと言っていいか分かりませんが、当時は単身赴任だったこともあり、自分の時間を自由に使うことができ、1週間に100時間以上を研究室で過ごしたこともありました。
こうして400例という前例のない規模の解析を行なった結果、ATLでは他の造血器腫瘍と比較して、多くの遺伝子変異や局所的なコピー数の異常、融合遺伝子があることを突き止めました。遺伝子変異の数は約50個で、その9割はATLで初めて同定された変異であり、2〜3割は他のリンパ系腫瘍でもこれまで報告がなかったものでした。これらの遺伝子異常は、ATLの病態や予後に影響していることも示唆されました。また、T細胞で重要な様々な遺伝子に、機能獲得型変異と考えられるホットスポットミスセンス変異などの繰り返し起こる遺伝子変異を見つけることもできました。
この結果は、2014年の第76回日本血液学会のPlenary sessionで報告しました。また、同年の第56回米国血液学会(ASH)でも、この結果をもとにATLで変異を認める遺伝子群が、T細胞にとって重要な経路に集積してくる点を発表しました。
ATLに関して、一定の研究成果が得られましたが、私は、ATLがHTLV-1の感染によることが日本で発見されたこと、さらに日本人に多い造血器腫瘍であることから、ATLは日本で解決すべき疾患であると考えています。そして、ウイルスに感染した人がすべてATLを発症するわけではないこと、感染から30〜50年後に発症することなど、ATLの全体像を解明することを次の目標にしました。
ATLで高頻度のPD-L1遺伝子異常を見出す
他の固形がんでも同様の機構で免疫回避
まず、ATL患者400例についての遺伝子解析データを、ゲノムの構造異常に着目して再解析することにしました。その結果、49例中13例(27%)でPD-L1遺伝子座の後半部分に切断点が集積するという構造異常を発見しました。これらの構造異常には、染色体の欠失や逆位、転座、重複など様々なタイプの異常が含まれていましたが、すべての例で、蛋白質に翻訳されない「3’-非翻訳領域」の欠損が起きていることが分かりました。また、PD-L1のコピー数にかかわらずPD-L1遺伝子の顕著な発現上昇が認められました。
3’-非翻訳領域で異常を認めた症例のうち、約半数ではPD-L1蛋白の構造が保たれていましたが、残りの約半数ではPD-L1蛋白が途中で切断されていました。実際、免疫染色で、腫瘍細胞のPD-L1の発現を検討したところ、構造異常のないPD-L1蛋白を発現する腫瘍細胞は、PD-L1の前半部分(N末端)、後半部分(C末端)を認識する抗体のいずれでも検出されましたが、3’-非翻訳領域の欠損のある例では、後半部分を認識する抗体では検出できませんでした。しかし、切断されたPD-L1蛋白も、正常のPD-L1と同様に機能することが確認されました。つまり、後半部分を欠失したPD-L1蛋白を発現するがん細胞も、免疫の監視機構から逃れていると考えられます。
これら一連のATLに関する解析から、PD-L1遺伝子の3’-非翻訳領域の異常を介した遺伝子発現上昇は、ATLだけでなく、様々ながん種で重要な免疫回避のメカニズムとなっていることが予測されました。そこで、米国のがんゲノムアトラス(The Cancer Genome Atlas:TCGA)に登録されている、33種類の悪性腫瘍からなる約1万例のがん試料の遺伝子解析データを用いて、PD-L1遺伝子の3’-非翻訳領域の異常の探索を行ないました。その結果、肺がん、胃がん、食道がん、直腸・結腸がん、腎がん、膀胱がん、子宮頸がん、子宮体がん、頭頸部がん、悪性黒色腫、肺腺がん、B細胞リンパ腫の12種類のがん種の計32症例で、PD-L1遺伝子の3’-非翻訳領域の異常が同定されました。
また、32例全例でPD-L1遺伝子の高度な発現上昇が認められ、このことは、ATLと同様にこれらのがん種においても、PD-L1遺伝子の3’-非翻訳領域の異常が遺伝子発現の調節に大変重要であることを示唆しています。そこで、これを検証するために、CRISPR-Cas9システムというゲノム編集技術を用いて、ヒトおよびマウス由来の様々な細胞株について、PD-L1遺伝子の3’-非翻訳領域の異常を導入して、それがPD-L1遺伝子発現に及ぼす影響を検討しました。その結果、PD-L1遺伝子の3’-非翻訳領域の異常を導入した細胞では、いずれも顕著なPD-L1の発現上昇が認められ、3’-非翻訳領域の異常が、一連のがんにおけるPD-L1遺伝子の発現上昇の原因であることが確認されました。
さらに、3’-非翻訳領域の欠失により、生体内でがん細胞にどのような結果がもたらされるかについて、マウスの移植モデルを用いて検証しました。マウスのリンパ腫由来の細胞株であるEG7-OVAをマウスの皮下に移植した後、免疫を促進させる薬剤(アジュバント)を投与してがん免疫を誘導することにより、腫瘍の縮小効果を、通常のEG7-OVA細胞と3’-非翻訳領域を欠失させたEG7-OVA細胞について検討しました。その結果、通常のEG7-OVA細胞を移植したマウスでは、がん細胞が縮小したのに対し、3’-非翻訳領域を欠失させたEG7-OVA細胞を移植したマウスでは、がん細胞の縮小はほとんど認められませんでした。
これらのことから、免疫チェックポイント阻害剤を用いることにより、PD-L1遺伝子の3’-非翻訳領域の異常を有するがんの治療が可能であることを示していると考えられました。さらに、PD-L1遺伝子の3’-非翻訳領域の異常は、抗PD-1抗体や抗PD-L1抗体による免疫チェックポイント阻害が有効な治療となる症例を見出すための有用なバイオマーカーとなる可能性があると思われます。この可能性については、少しでも早く、臨床試験で検証されることを期待しています。
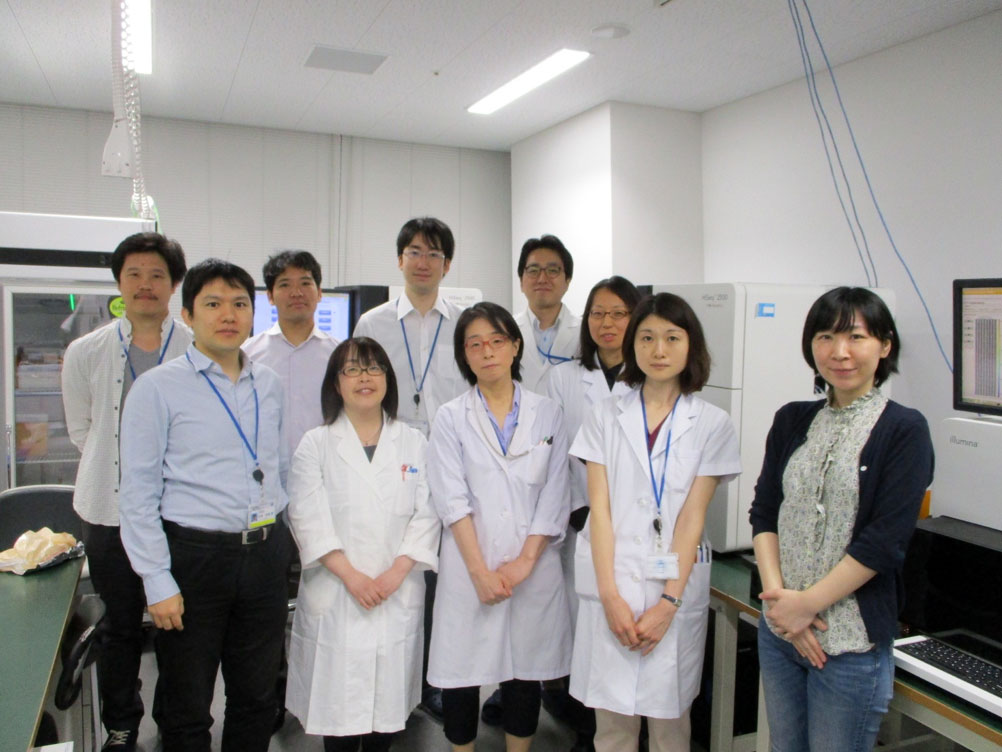
〈後編では、片岡先生が血液内科の道に進まれたきっかけや数々の出会い、また現在取り組まれているご研究の一つである遺伝子解析パネルについて語っていただきました。〉