造血、骨細胞、ニッチ、末梢神経の関連を追究
研究成果を造血器腫瘍の解明に生かし治療介入に挑む(前編)
淺田騰(岡山大学 学術研究院 医歯薬学域 血液・腫瘍・呼吸器内科学 准教授)
2025.08.21
血液内科医として5年間勤務した後、岡山大学大学院に進学し、神戸大学血液内科で骨髄における造血幹細胞と骨細胞との関連についての研究を開始した淺田騰氏。その後、米国で骨髄内ニッチ、さらに末梢神経系による造血調節のメカニズムの解明に取り組み、一連の研究成果は国際的に高く評価されている。岡山大学に戻った現在は、これらの基礎研究を白血病など造血器腫瘍の病態解明に生かし、ニッチを介した病態制御の研究に取り組んでいる。

岡山大学を2003年に卒業後、初期研修、後期研修で臨床医として5年間勤務し、6年目から神戸大学血液内科での研究生活に入りました。研究テーマは、血液細胞・造血幹細胞に対する骨細胞の役割です。まず顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)による造血幹細胞動員の機構と、造血制御への関与を研究しました。G-CSF大量投与による末梢血への造血幹細胞の動員の機序を解明するとともに、骨髄内の骨芽細胞ニッチが造血システムの制御に関与していることを明らかにしました。この研究結果は学位論文となりました。
2013年からは米国・Albert Einstein College of MedicineにResearch fellowとして勤務し、引き続き、骨髄内の血管を取り巻く環境に存在するニッチ細胞と、造血幹細胞の制御機構について研究を進めました。その結果、骨髄内の血管周囲細胞群が造血幹細胞を複雑に制御していることを明らかにしました。その後、骨組織にも分布する末梢神経系による正常造血制御のメカニズムも明らかにし、造血は骨細胞、ニッチ、末梢神経によって細やかに調節されていることを解明し、これらは大学院で始めた研究テーマの集大成となったと思います。
個人での研究はここで一区切りとし、現在はチームとして、白血病など造血器腫瘍におけるニッチや末梢神経シグナルの関与などの研究を進めています。
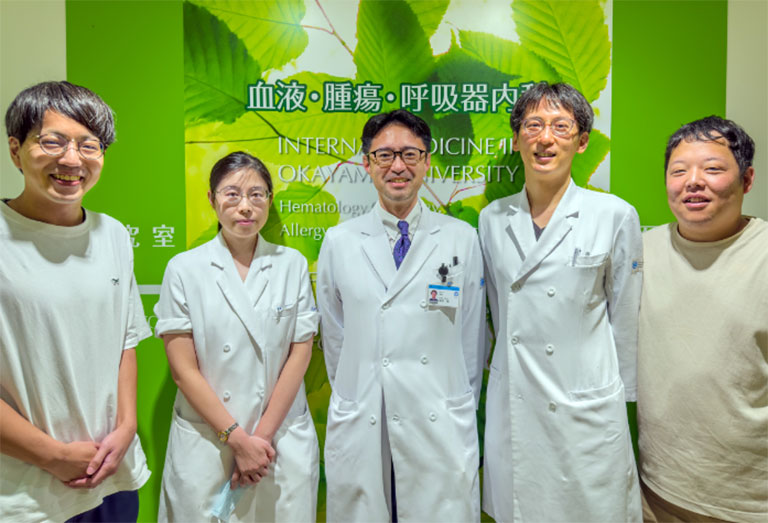
岡山大学卒業後すぐに亀田総合病院で研修
多くの疾患を診療し、論文を書く大切さを学ぶ
私は香川県の出身で、県立高松高校を卒業後、岡山大学医学部に進学しました。医師になると決めたのは中学2〜3年生の頃で比較的早かったと思います。子供の頃は病気がちで、入院することもしばしばで、実はリンパ節生検を受けたこともあります。母が看護師だったこともあり、医療や医師は常に身近な存在でした。なかでも印象的だったのは、医師が子供には手の届かない洒落たボールペンを使い、カルテに英語やドイツ語をさらさらと書いていく姿で、その姿はとても格好良く、憧れました。
高校3年のときに岡山大を目指すことを決めセンター試験に臨みましたが、結果は散々でした。でも諦めず二次試験を受け、一次試験の失敗をカバーすることができ1997年に第一志望の岡山大に入学しました。
血液内科に進もうと決めたきっかけは、臨床実習などで造血幹細胞移植という治療法を知ったことでした。また、造血器腫瘍はがんでありながら、内科医だけで治せることが驚きであり、患者さんは若い人も多く、こうした人を救えるという仕事にやりがいを見出したのです。2003年の卒業後は、スーパーローテートができる病院で初期研修を受け、臨床医を目指すことにしました。そして岡山大第二内科に在籍しつつ、千葉県鴨川市の亀田総合病院を受験し合格することができました。
亀田総合病院では、全国から集まった数十人の同期医師や先輩医師と切磋琢磨し、多くの刺激を受けながらハードな2年間の研修を受けました。2005年からは後期研修医として、血液・腫瘍内科に勤務し、様々な血液疾患の患者さんを数多く診療しました。
当時、血液内科には約100床の病床があり、部長の末永孝生先生も含めて6〜8人で診療するという体制で大変多忙な日々でした。そのような状況でも末永先生には、臨床経験を論文にすることを強くご指導いただきました。「患者さんを一生懸命に診ることで、必ず新しい発見がある。それを形にしなさい」という教えでした。
研究にも力を入れていて、私は末永先生や同僚らとの共著「血管内大細胞型B細胞リンパ腫の診断とランダム皮膚生検の有効性」の執筆に携わり、これは2007年に「Mayo Clin Proc」に掲載されました。臨床面でも研究面でも亀田総合病院でいろいろと仕込まれました。末永先生から「臨床医になるにしても、人生の中でどこかで基礎研究に取り組んだ方がいい」とのアドバイスもあり、2007年に岡山大病院血液・腫瘍内科に戻り、1年間臨床医として勤務した後、翌2008年に大学院に入学しました。ここからが私の研究生活の始まりです。


神戸大学大学院に国内留学
血液細胞、骨細胞、神経の関連が研究テーマ
研究は、神戸大学大学院血液内科に国内留学し片山義雄先生のご指導を受けることになりました。そしてここで私は、その後のライフワークとなる、造血システム、骨細胞、ニッチ、末梢神経の研究に出合いました。
片山先生は岡山大学第二内科のご出身ですが、私が岡大病院の血液内科に勤務していたときは神戸大にいらっしゃいました。そして週に1回、岡山大の大学院生を指導されており、私は先輩から「レベルの高い様々な研究の話を聞けるから、参加しないか」とミーティングに誘われました。実際、片山先生の話は、臨床の世界しか知らない私にはどれも興味深い内容でした。そこで、大学院に進むにあたり、片山先生の指導・教育のもと研究に取り組みたいと考えたのです。
また、こうした私の要望を受け入れ、後押ししてくださったのが、当時第二内科教授の谷本光音先生でした。医学部卒業後、入局はするけれど初期研修は亀田総合病院で受けたいという私の願いを聞き入れてもらうなども含め、希望することをさせていただき大変感謝しています。
神戸大での生活は、週1度の外勤のほかはほとんどの時間を研究に費やしました。片山先生にはマンツーマン、文字通り手取り足取りの指導をいただきました。動物実験で毎朝晩に投薬の必要があったりしてほとんど毎日実験に取り組んでいました。ただ、そこまで指導していただいたのに、最初の研究テーマでは、1年半近くポジティブデータが得られず行き詰まりました。そこで、片山先生から新たに提案されたのが、血液細胞、骨細胞、神経との関連を探るというテーマでした。
すべての血液細胞のもととなる造血幹細胞は、骨髄中の“ニッチ”と呼ばれる特別な場所にいることが知られていました。G-CSFは造血幹細胞をニッチから引き離し、末梢血中に誘導(動員)できますが、当時そのメカニズムは詳しくは解明されていませんでした。また、ニッチを構成する細胞のうち、骨内膜にある骨芽細胞については造血幹/前駆細胞の動員メカニズムに関与することは知られていたものの、骨組織の内側にある骨細胞が血液細胞に及ぼす役割については研究されていませんでした。
近年の研究から、骨細胞が骨への荷重の感知、骨リモデリングの調節、カルシウムやリンなどのミネラルバランスの調節など、生体内で多くの重要な役割を担っていることが分かってきました。そこで私たちは、G-CSFによる造血幹細胞動員メカニズムにおける骨細胞の役割を通して、その造血制御への関与をマウスを用いて検討することにしました。
まず、野生型マウスにG-CSFを12時間おきに8回投与したところ、骨芽細胞は6〜8回投与後に抑制されるのに対し、骨細胞は1回目の投与で抑制されることが分かりました。さらに研究を進め、骨細胞が交感神経による調節を受けること、骨細胞を特異的に除去したマウスではG-CSFによる造血幹/前駆細胞の動員が障害されること、骨細胞除去マウスでは骨芽細胞と骨髄内微小環境が変化していることなどを明らかにしました。
さらに研究と考察を進め、G-CSF投与時には、骨芽細胞は、交感神経から放出されるカテコラミンシグナルを受けて直接抑制を受ける経路、G-CSFにより抑制を受けた骨髄マクロファージからのサポートシグナルを失う経路に加え、この研究で明らかになったカテコラミン刺激により骨細胞が抑制される第3の経路があり、3方向からの抑制を受けることでニッチ機能の破綻につながり、造血幹/前駆細胞が動員されることを解明しました。
それまで造血システム制御への関与が不明だった骨細胞の新たな機能を明らかにした意義は大きく、これらの結果をまとめたものが私の学位論文となり、2013年の『Cell Stem Cell』誌に「Matrix-embedded osteocytes regulate mobilization of hematopoietic stem/progenitor cells」のタイトルで掲載されました。
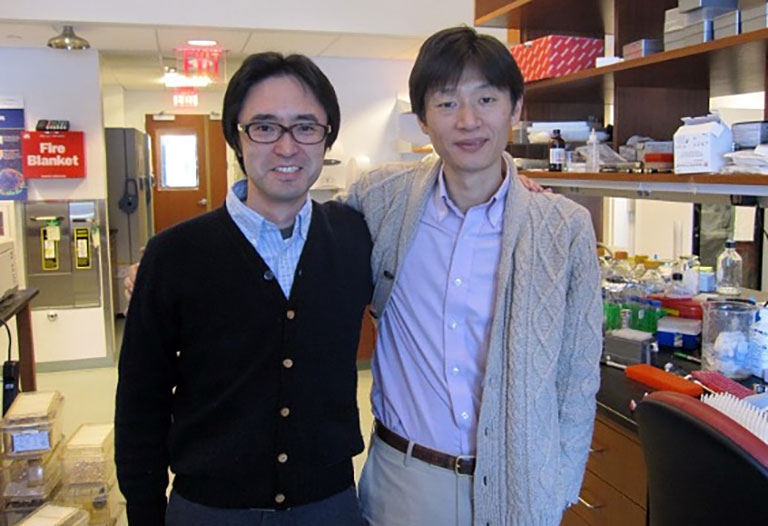
〈後編では、米国留学のお話や、国際学会での受賞、帰国後に取り組んでいる研究について語っていただきました。〉