豪州に渡って5年、独立してラボを持つ
骨髄腫の腫瘍免疫を中心に研究を進める(前編)
中村恭平(クイーンズランド医学研究所(QIMRB) 主任研究員)
2021.05.13
2020年6月にオーストラリア・クイーンズランド医学研究所(QIMRB)の主任研究員(PI)としてラボを開設した中村恭平氏。東北大学でNK細胞の研究をし、その後、腫瘍免疫の研究に転じた。海外で自立できる力を身に付けるべくオーストラリアに留学、5年後にPIとなった。研究成果の臨床応用も視野に入るが、まずは腫瘍免疫の基本メカニズムの解明を進めていくという。
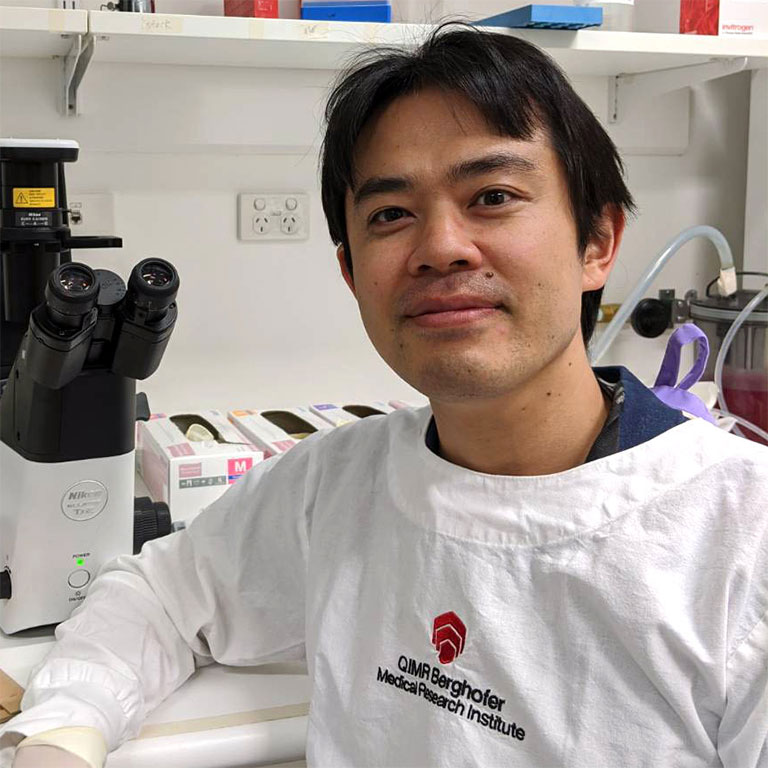
2015年4月にオーストラリアのクイーンズランド医学研究所(QIMRB:QIMR Berghofer Medical Research Institute)に博士研究員として留学し、6年目になる2020年6月に主任研究員(PI)として“Immune Targeting in Blood Cancers Laboratory”を開設しました。私のほかに、ポスドク、実験助手、学生の合わせて4人の小さなラボですが、皆優秀で助けられることが多く、研究しやすい環境になったと実感しています。
QIMRBは、オーストラリア北東部、グレートバリアリーフで有名なクイーンズランド州の州都ブリスベンにあります。クイーンズランド医学研究所(QIMR:Queensland Institute of Medical Research)は1945年に設立されて以来、研究領域を広げ、近年はゲノム解析分野で業績を上げ、医学研究の世界ランキングでは上位にランクしています。2013年にClive Berghofer氏が巨額の寄付をしたことから名前がQIMRBとなりました。
独立したことで、ポスドク時代に比べ緊張感がより高まっていますが、新しいプロジェクトも立ち上げ、これまでに描いてきた青写真を少しずつ実現していきたいと考えています。

仙台に生まれ30年以上を過ごす
医学部3年のときに免疫に興味
私は生まれも育ちも宮城県仙台市で、地元の幼稚園、小・中学校に通い、仙台第二高校を卒業しました。1年間の浪人生活の後、2002年に東北大学医学部に入学しました。医学部に進んだのは、純粋に医師という仕事に憧れていたからです。医学研究を通して病気を理解し治療に関わるというのが、私が抱いていた医師のイメージです。しかし、実際に医学部に進んでみると、おそらく多くの医学部生と同じように、「難しそうな基礎研究は自分には向いていないなあ」と感じるようになりました。
3年生では「基礎医学修練」という3カ月だけ自分の興味のある研究室で学べるカリキュラムがあり、私は免疫の研究をしている高井俊之先生の研究室に入りました。非常にレベルの高い研究室であり、のんびりした学生生活を送っていた自分には研究内容がよく分からないのは言うまでもなく、仕事の効率化を図りながら、膨大な知識をもとに次の研究テーマを探索していくその早さに、ついていけませんでした。
ただ、日本免疫学会に参加させてもらい、そこで聞いた免疫の話は面白く、がんや自己免疫疾患だけでなく、動脈硬化や糖尿病などいろいろな病態に関わっていることを知り、自然免疫や炎症に強い興味を持ちました。
卒業後の初期研修は、大崎市民病院で受けました。内科の研修はどの診療科も面白かったのですが、2年間の研修後、再び免疫学会に参加してみることにしました。そこで、やはり免疫や炎症という視点で病気をみていきたいという気持ちを確認し、後期研修は大崎市民病院のリウマチ内科で外来診療のマネジメント、重症者の診療などに携わりました。
半年間の後期研修後に、張替秀郎教授の率いる東北大学の血液・免疫病学分野の大学院に進学することにしました。仙台での生活はそれまで28年間続き、さらに4年間、仙台で暮らすことになりました。
大学院は加齢医学研究所の研究室に
NK細胞の研究を機に興味は腫瘍免疫に
大学院には2011年秋に入学し、最初の1年間はリウマチ膠原病の病棟に勤務しました。
特に臨床経験で実感したことは、膠原病などで炎症性疾患は、慢性的な炎症が長期にわたるために細胞にダメージが与えられ、様々な臓器障害に加えて、健康な人と比較して発がんリスクが高まるということでした。また、自己免疫疾患の治療には免疫抑制剤が必要不可欠ですが、長期的な免疫抑制状態は、やはりがんのリスクを高めてしまいます。腫瘍免疫学の観点からすれば、前者は“Tumor-promoting Inflammation”と呼ばれる「がん促進性の炎症」、後者は“Cancer Immunosurveillance”と呼ばれる、「がん免疫監視理論」という概念で説明されます。もちろん、臨床医として働いていた当時は、これらの概念は知りませんでした。しかし後に、臨床で生じた自分の疑問を明快に説明するこれらの概念と出合い、強い影響を受けました。この2つの概念は、今でも自分の研究のキーワードになっています。
研究は、血液免疫病学から加齢医学研究所に出向して、生体防御学の小笠原康悦先生のもとで始めました。少しでも腫瘍免疫応答に関わる研究がしたいと思い、NK細胞をテーマに選びました。そして2014年9月に「細胞間膜分子移動を介したNK細胞の運命制御」というテーマで学位を取得することができました。NK細胞は事前の感作を必要とせず、速やかに細胞傷害活性を発揮できることから、がん免疫監視機構の最前線で機能しているリンパ球と位置づけられています。私は、NK細胞の代表的な活性化受容体であるNKG2D受容体を中心に研究を行ないました。NKG2D受容体は、ウイルス感染やがん化によって誘導される標的分子のNKG2Dリガンド(NKG2DL)を認識し排除することから、NK細胞の活性化機能の中心的役割を担っています。そして、このNKG2D受容体−NKG2DLの相互作用は「免疫シナプス」と呼ばれるNK細胞−がん細胞間の密な接触と高次構造の形成をもたらします。
私は、この免疫シナプスでNK細胞が、がん細胞上に発現する標的NKG2DLを獲得して、NK細胞自身の表面上にNKG2DLを提示することに着目し、がん細胞表面の標的膜分子を外因性に獲得したNK細胞は、他のNK細胞によって細胞傷害活性を受け、細胞死に至ることを明らかにしました。さらに、こうしたNK細胞とがん細胞のダイナミックなクロストークが、がん微小環境におけるNK細胞をはじめとする免疫応答制御に重要な役割を果たしている可能性も見出しました。
大学院時代に行なったNK細胞の研究は、2013年のニューオリンズで開催された米国血液学会(ASH)に採択され、もう一つの炎症に焦点を当てたプロジェクトは、翌年のサンフランシスコで開催されたASHに採択されました。ASHでは、免疫学にしても、分子生物学にしても、病態の解明や治療開発に主眼を置いた研究発表が多く、今後自分のやっていきたい研究のイメージが見えてきました。また、ちょうど造血器悪性腫瘍に対する免疫チェックポイント阻害剤や二重特異性抗体等の免疫細胞療法の臨床試験が始まった時期であり、免疫療法のうねりを感じました。
歴代ノーベル賞受賞者らから大きな刺激
渡豪し、がん免疫監視機構の研究へ
30年間仙台で暮らしていた私が海外留学しようと決意したのは、日本学術振興会の推薦によって、2014年6月に開催された第64回リンダウ・ノーベル賞受賞者会議に参加したことでした。ドイツ・ミュンヘンから電車で2時間ほどのリンダウという街で開かれるこの会議は、毎年約30人のノーベル賞受賞者と、各国約10人の若手研究者を合わせた500人ほどが招かれ、受賞者の講演を聞いたり、受賞者や若手研究者が交流するイベントです。
5日間の会期中、連日午前中は8人のノーベル賞受賞者が各30分の講演を行ない、午後には受賞者が若手研究者の質問に気軽に応じる時間があります。さらに夜のパーティーでは、受賞者と参加者がリラックスして研究内容や今後の目標などについて話し合います。これらの交流を通じて、長年同じ国に住み他国の研究の状況も知らず、自分の視野がいかに狭かったかを思い知らされました。数日間で大きな刺激を受け、もっと研究の道を進んでいきたい、もう少し頑張っていろいろな研究をやってみたいと強く思いました。
それまでの自分は、数年先のことしか見ておらず、それに比べ海外の若手研究者は中長期的な視点でビジョンを描き、自信に満ちあふれていました。新しい研究テーマを見つけるには、広い視野を持ち、海外で自立できる力を身に付ける必要があることも痛感しました。一刻でも早く留学し、そういう環境に身を置こうと決意しました。リンダウでの会議を終え、ミュンヘン空港でのビアガーデンで、3時間ほど一人でビールを飲みながらの決意でした。

懇親会ではそれぞれの民族衣装を披露しました(私は前列左から2人目)。
〈後編では、留学先で3カ月かけて研究の構想を練ったことや、グラントを獲得し独立するに至った経緯などについて語っていただきました。〉