「白血病を治す医師になりたい」
初志を貫き、移植医療の進展と普及に尽力(前編)
原田実根(唐津東松浦医師会医療センター 院長、九州大学 名誉教授)
2019.11.07
「この人に聞く」のシリーズ第10回では、九州大学名誉教授の原田実根氏にお話をうかがいました。医学部紛争の最中に九州大学を卒業、同大附属病院で4年間臨床研修を行なった後、金沢大学に移り、骨髄移植黎明期から移植医療に取り組んだ原田氏。米国留学を経て九大に戻り、その後岡山大に赴任し、再び九大に戻りました。その間、末梢血幹細胞移植など様々な造血幹細胞移植法の確立に尽力するとともに、現在、移植分野の臨床・研究の第一線に立つ多くの医師を指導・育成してきました。「夢を描き、追い求めればこそ、得られるものがある」と話します。
原田実根(唐津東松浦医師会医療センター 院長、九州大学 名誉教授)
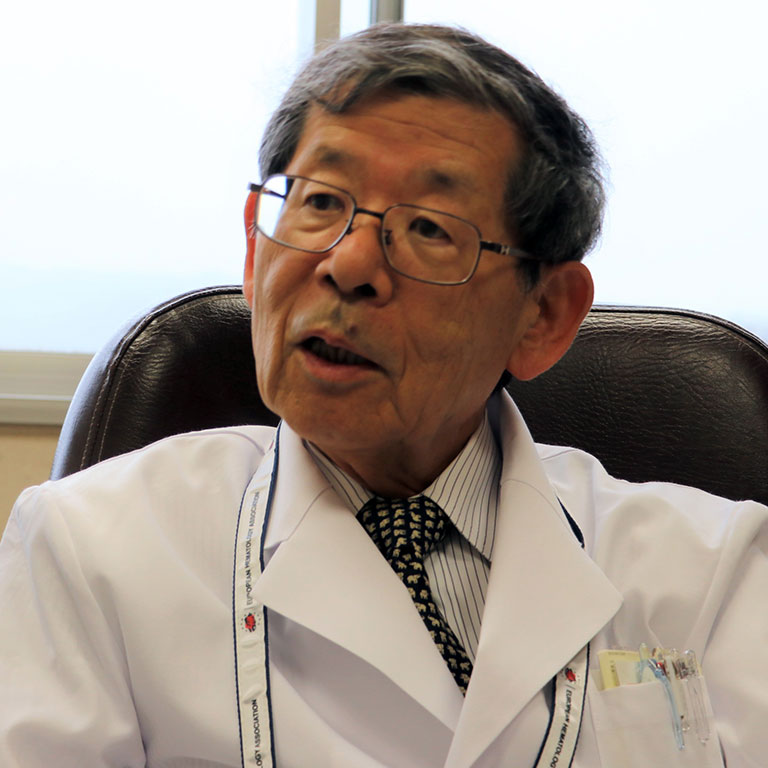
1943年福岡市生まれ。68年九州大学医学部卒業後、同大附属病院研修医、70年同病院内科医員。72年金沢大学医学部第三内科医員、73年同大助手、75年同大輸血部講師。78年米国・カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)医学部内科血液腫瘍学部門留学(2年間)。83年金沢大学医学部講師。87年九州大学医学部講師、91年同大助教授。94年岡山大学医学部第二内科教授。2001年九州大学大学院教授(医学研究院病態修復内科学分野)。07年国立病院機構大牟田病院院長、12年より現職。
九州大学を卒業後、同大附属病院で2年間の初期研修、2年間の後期研修(医員)の後、金沢大学に赴任、米国留学を経て、九大に講師として出戻りました。その後、岡山大学の教授を務め、再び九大に出戻るという経歴をたどりました。この間、私が一貫して取り組んだのが造血幹細胞移植の研究と臨床です。振り返れば、どの場所でも新しいことを始める機会が与えられ、良き仕事仲間に恵まれてきました。そして今なお「白血病を治す医師になりたい」という初心を忘れてはいません。
卒業後は入局せずに研修を受ける
金沢大で出合った骨髄移植
私が九大を卒業した1968年は、全国の大学で医学部紛争が活発に繰り広げられていた頃でした。九大も例外ではなく、インターン制度の廃止を求めて、私達は授業をボイコットし、ストライキを打ち、デモに参加し、そして国試もボイコットしました。制度廃止を求める全国の医学部学生や医師に対して、文部省(当時)と厚生省(当時)が示したのは「医員」といういわば「日雇い」の仕組みでした。これに私たち学生は猛反発し、「九大の医局には入局しない」ことをクラス討議で決議しました。出身大学の医局に入らない、という動きは全国的なものでした。
クラス決議通り、私は卒業後どの医局にも入局せずに九大病院に居座って闘争を続けました。一方で、公認されないまま、自分達の研修プログラムに従って、第一内科、第二内科、第三内科、小児科を半年ずつローテートして2年間の卒後研修を済ませました。3年目からは、居心地のよかった第一内科病棟に居座って、2年間医員として研修を続けました。私は開業医の息子で、父の跡を継ぐつもりで医学部に進みましたが、入学した年に父が亡くなり、跡を継ぐ必要がなくなっていました。こうした身軽な立場だったこともあり、この研修のしかたでも「何とかなるだろう」と悲観はしていませんでした。
血液内科に興味を覚えたのは、学生時代のときです。ベッドサイド・ティーチングで担当した、健康優良児の小学6年の男の子が、急性骨髄性白血病であっけなく亡くなったことに衝撃を受けました。研修医時代も九大病院内科医員のときも、たくさんの白血病患者さんを受け持ちました。そうして様々な臨床経験を積むうちに「白血病を治す医師になりたい」と強く思うようになりました。
しかし、九大の内科には入局しない、と決めていたので、白血病の臨床・研究をする場所を探さなくてはいけませんでした。ちょうどその頃、学生時代に血液学の講義を受けた服部絢一先生が金沢大学第三内科を創設されたばかりで、人材が不足していると先輩が教えてくれました。そこで早速面接試験を受け、何とか金沢大の医員として採用してもらい、1972年4月に金沢に移りました。服部教授からは「もう、紛争を起こさないように」と釘を刺されました。また、「私は九大出身であるが、私が君を招んだのではなく、君が勝手に希望して来たのだから、そこのところを履き違えないように」と服部先生に言われました。この言葉は、その後私にとって大きな支えとなりました。
金沢大学では血液学の勉強に本格的に取り組みました。半年ほど経った頃、服部先生からテーマを決めて研究をするように指示され、米国留学から戻られたばかりの滝口智夫講師に相談したところ、「骨髄移植の基礎的研究」というテーマをもらいました。移植片対宿主反応(GVHR)の予防に関する研究をマウスモデルで行なうというもので、なかなか面白そうだと思いました。これが私と骨髄移植との出合いです。
最初の成功例を見届け米国へ留学
研究の傍らカンファレンスにも出席
滝口先生はやがてオランダに留学されたため、実験に行き詰まったりしたときには金沢大学がん研究所の右田俊介先生の研究室に相談に行きました。その折々に研究所のいろいろな先生から免疫学のABCを教えてもらい、耳学問ではありましたが、それは、骨髄移植の臨床応用に取り組むようになってからとても役に立ちました。
わが国の骨髄移植の臨床応用は、1970年代半ばから、金沢大学、名古屋大学、大阪府立成人病センターで始められました。私の骨髄移植の基礎研究がまとまりかけた頃、金沢大第三内科では骨髄移植の臨床応用の実現に向け、教室が一丸となっていました。何もないところからわが国初の骨髄移植を成功させようとする服部先生の意気込みはすさまじく、その情熱は移植医療に対する私の姿勢に大きな影響を与えました。
1977年に第39回日本血液学会総会が金沢で開催され、会長の服部先生は米国からE. Donnall Thomas 博士を招待し、特別講演が行なわれました。その内容はわれわれに強いインパクトを与え、わが国の造血幹細胞移植の夜明けを告げるものとなりました。私は金沢でのThomas先生のお世話係を仰せつかりました。朝、ホテルにお迎えに行き、夜は宿にお送りするという、貴重な数日間を経験しました。
私はすぐにでも、Thomas先生のいるシアトルのフレッド・ハッチンソンがん研究センターに留学したくなり、Thomas先生にお願いの手紙を書きましたが、空きがなく、1年間待ってほしいとのことでした。実は、私の娘が小学校に上がる年で、1年間待つと2年生からの転入となり、周囲に溶け込むのに時間がかかるだろうと考え、すぐに留学できる施設を探しました。留学のアプリケーションを10通ほど出して、最初に返事が来たカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)医学部内科血液腫瘍学部門に1978年に留学することにしました。
UCLAでは、Robert Peter Gale先生が私のボスでした。スマートな頭の持主で2歳年下でした。研究テーマは、抗胸腺細胞グロブリン(ATG)の臨床応用のための予備実験でした。ヒトの血液を使って研究に取り組む一方で、UCLA骨髄移植チームの回診やカンファレンスにも必ず参加し、骨髄移植のノウハウを少しでも多く身につけようとしました。UCLAの骨髄移植の件数はシアトルに次いで多く、効率良く動くシステム、優れた人材の多さ、潤沢な研究費など、わが国とは比べものにならない環境に目を見張りました。
2年の留学期間の終わりが近づいた頃、Gale先生からは「もう1年、研究を続けてほしい」と言われましたが、服部先生からは「ここで戻らないと、助手のポジションがなくなる。クビにするぞ」と言われ、日本に帰ることにしました。
金沢大に戻ったら、骨髄移植の臨床に一生懸命取り組もうと強く思っていました。教室には移植に関心を持つ若い医師が増えており、移植への情熱を感じるとともに、競争意識も強く、意気盛んな教室になっていました。

「九州でも移植を」との誘いで古巣へ
末梢血幹細胞移植の臨床応用を開始
1983年に金沢大講師となり、医局長を3年ほど務めた頃、九大第一内科の柳瀬敏幸教授の後任の仁保喜之教授から「九州でも移植を始めませんか。戻って来ませんか」と声が掛かりました。気がつけば、九大を出て15年近くが経っていました。迷いはありましたが、「君が帰ってくるなら、準備を進めましょう」とのひと言で九大に戻ろうと決心し、1987年に母校に帰りました。
ところが、帰ってみると無菌室はなく、移植の準備はほとんど進んでいませんでした。話が違うと思いましたが、福岡で常に先進的な医療に取り組んでこられた原三信病院の院長先生に移植に必要な無菌室の設置をお願いに仁保先生と一緒に伺いました。そこで、第15代原三信院長は即断即決、快く引き受けてくださいました。まずは、原三信病院で移植を行なう準備を進め、1989年に九州初の骨髄移植を行なうことができました。その後、第一内科にいた谷口修一先生(現・虎の門病院)が浜の町病院の骨髄移植室長となり、浜の町病院でも1990年から骨髄移植が開始されました。
こうして九大第一内科を中心に骨髄移植施設が増えていきました。私は、谷口先生をはじめ、赤司浩一先生(現・九州大学)、豊嶋崇徳先生(現・北海道大学)など、頼りになる優秀でガッツのある若い仕事仲間に恵まれていました。骨髄移植が普及していくなか、骨髄移植とは違う、新しいことを始めたいと考えていた私は、ある文献で末梢血幹細胞移植(PBSCT)のことを知り、しかも1988年に徳島大学の小児科からわが国の第1例が報告されていて、「これだ!」と思いました。輸血部長の稲葉頌一先生の全面的な協力のもと、第一内科の若手らによる前臨床的検討が精力的に進められ、思いのほか早く1989年に自己PBSCTの臨床応用を開始することができました。
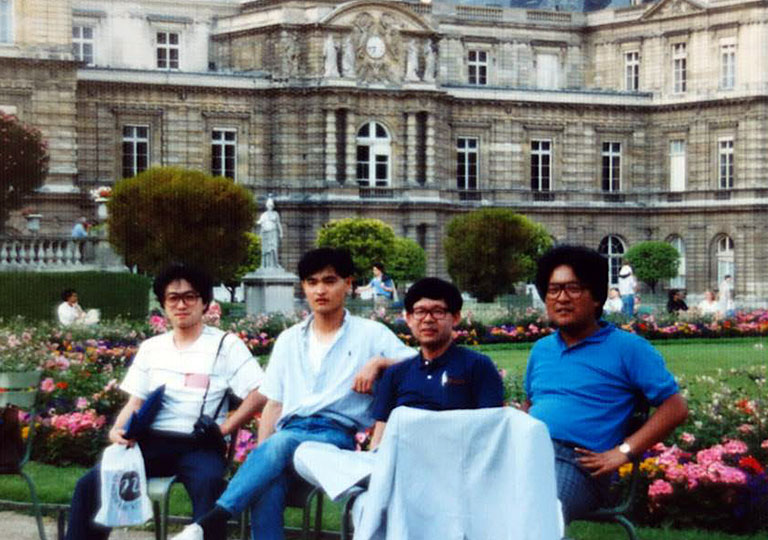

〈後編では、岡山大学への赴任、そして思いがけないかたちで九州大学へ再び戻られることになったエピソードを語っていただきました。〉