NK細胞と出合い、腫瘍研究の道へ
「血液学はいつまで経っても面白い」(前編)
押味和夫(つるい養生邑病院 内科)
2018.11.15
「この人に聞く」のシリーズ第5回は、順天堂大学血液内科の初代教授を務めた押味和夫氏を紹介する。「いい臨床医になること」を目指して、大学卒業後まもなく米国に渡り、臨床経験を積む中で基礎的研究に興味を持った押味氏が、帰国後に出合ったのがNK細胞だった。その後、NK細胞由来の悪性リンパ腫や白血病の研究がライフワークとなった。北海道・釧路郊外で釣り三昧の生活を送りながら、今なお血液学を学び、診療を続ける押味氏に話をうかがった。
押味和夫(つるい養生邑病院 内科)
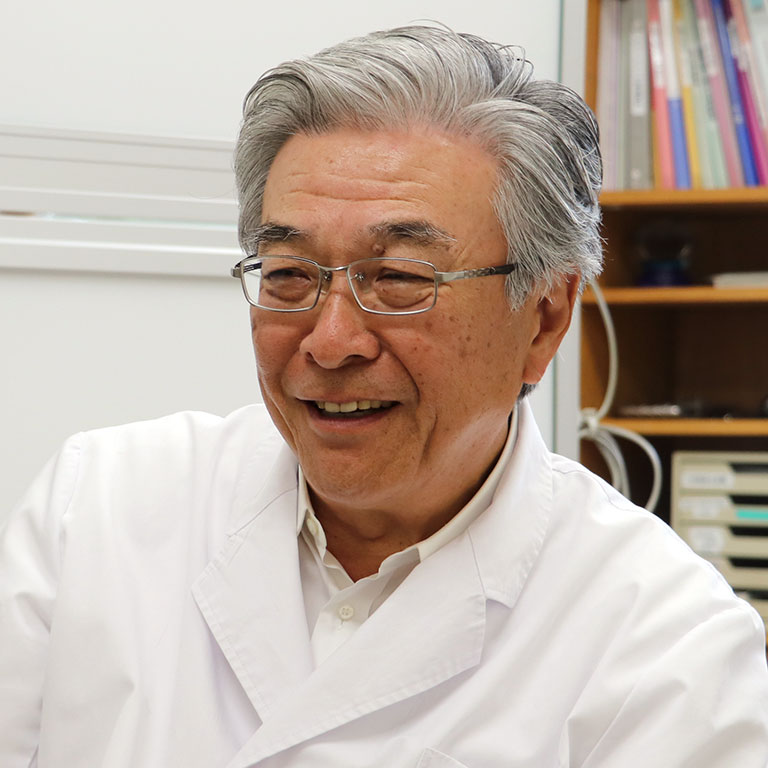
1944年福島県生まれ。1971年東京大学医学部卒業後、1972年7月米国で内科インターン、1973年レジデントに。1974年7月東京大学医学部附属病院第三内科医員。1974年11月自治医科大学アレルギー膠原病科助手、1978年4月同講師。1980年10月東京女子医科大学血液内科講師、1988年2月同助教授、1992年8月同教授。1994年4月に順天堂大学医学部血液内科教授。2008年より、米国エーザイの研究所で抗がん剤の開発に従事。帰国後、北海道阿寒郡鶴居村に移住。地元の2つの病院で非常勤の医師として勤務しながら、釣りやカヌーを楽しんでいる。
もともと先が読めない、想像力がないため、人とは違う経験を積んできたかもしれません。いい臨床医になることを目指し、米国で臨床研修を受けたものの、帰国後に、新たに発見されたNK細胞に出合い、自治医科大学、東京女子医科大学、順天堂大学と移りながら、臨床と研究の両方に興味を持った生活を数十年送りました。
現在は、北海道釧路市に隣接する鶴居村に居を構え、週に3日、診療現場で働き、あとは釣り・カヌー、それに少しの血液学勉強という生活を送っています。毎年夏、鶴居村で「Tsurui Lymphoma Workshop」という研究会を開催し、全国から集まった医師やコメディカル、その家族ら総勢80人前後で、勉強も野外活動も楽しんでいます。血液学はいつまでも面白いと実感しています。
医療も英語も分からぬまま米国の病院へ
2年目には早くもインターンの教育も
私の父は福島の田舎の開業医で、伯父は東北大学抗酸菌病研究所(現・加齢医学研究所)の病理にいました。親戚には医師が多く、将来、自分が医師になることにあまり疑問は抱きませんでした。1964年に東京大学に入学し、医学部に進学してからは「研究の道に進んでも、自分の能力では大した研究者にはなれない。それより少しでも多くの患者さんを助けられる、いい臨床医になろう」と決意しました。
1971年に卒業し、1年間東大病院で研修を受けた後、米国での2年間の内科研修を志願、1972年7月から米国・ニュージャージー州ニューアークのNew Jersey College of Medicine and Dentistryでインターンの研修を受けることにしました。英語はろくに話せませんでしたが、「米国の実地で覚えればいい」と気楽に考えていました。これが、とんでもないことになるとは、ちっとも想像しませんでした。
研修が始まる数日前に、手続きのために病院の事務室へ行ったのですが、担当者の英語が全く分かりません。先方もびっくりして整形外科医の日本人を通訳として呼び、何とか手続きは終えました。さすがの私も、少し不安になってきました。
インターン2カ月目にCCUに配属されました。心配していた通り、患者さんの訴えが理解できません。患者さんも何とか私に分かってもらおうと必死に説明し、何とか訴えが分かっても、心電図が読めませんし、不整脈の薬をどう使えばいいのかということも分かりません。「もっと準備とトレーニングをしておけばよかった」と、先を読めない性格を悔やみましたが、前に進むしかありません。
病棟回診ではベッドサイドで教授が順番にインターンに質問するのですが、私は教授の質問の意味を理解するのに時間がかかり、答えを考えているうちに、次のインターンへの質問に移ってしまいます。また、当直のとき看護師からの電話で起こされ、「患者が出血している(The patient is bleeding.)」と聞こえたので、慌てて病室に駆けつけると、患者さんは呼吸をしておらず、脈も触れません。亡くなっていたのです。そこで看護師に「この患者は亡くなっている。出血はしていない」と言いました。すると彼女はこう言いました「私は、“The patient ceased breathing.”(患者さんが息を引き取った)と言ったのだ」と。
同じような毎日が続き、一時は本気で日本に帰ろうと考えましたが、何とか1年、踏ん張りました。最初に指導を受けた教授から「ずいぶん良くなったな」と言われたときには、とてもうれしく思いました。
米国での2年目の研修は、ケンタッキー州ルイビルのUniversity of Louisville, School of Medicine で受けました。2年目はレジデントですから、インターンを教えないといけませんし、学生も付きます。今から思い返すと、よくまあ務まったものだと自分でも信じられないほどです。あるとき、学生と一緒に教科書のどこに目指す内容が書いてあるかを見つけようと、そろって読み始めました。そして彼が「ここにある」と言った場所は、私が読んでいるところから3倍も先でした。彼らを凌駕するには3倍以上勉強しなければいけないと思いました。
こうして、何とか2年間の研修を終えて帰国する頃には、憧れてやって来た米国が大嫌いになっていました。「今に見ていろ。米国をやっつけるぞ。日本国内で足の引っ張り合いをしている暇はない、団結して米国に対抗するんだ」。こんな思いを胸に帰国の途に就きました。
帰国後、発見されたばかりのNK細胞に飛びつく
女子医大に移り血液の臨床と研究に注力
米国で臨床経験を積んだら、臨床だけでは物足りなくなり、それまで興味のなかった基礎的な研究にも携わりたいと思うようになりました。医者になるなら、がんに取り組みたいと考えていたこともあり、免疫学の黎明期だったこともあって、がんを免疫で治せないかと思いました。東大第三内科から自治医大に移り、狩野庄吾先生に師事し、がん細胞に特異的なキラーT細胞を誘導する研究に取り組む一方、同大アレルギー膠原病科で診療することにしました。
私はそれまで膠原病の患者さんを診たことがなく、臨床は面白く、わくわくする毎日でした。一方、マウスを使ってのキラーT細胞はなかなか誘導できず、行き詰まりかけていました。そこへ、東京かどこかの研究会から戻った狩野先生が、「北欧の研究者が、NK(natural killer)細胞という細胞を発見した」と教えてくれました。そこで勝手に研究の目標をこの細胞に変えてしまいました。
「自然の殺し屋」という言葉に惹かれ、私はすぐさま、会ったこともないスウェーデン・カロリンスカ研究所のGeorge Klein先生に「ヒトとマウスのそれぞれのNK細胞に感受性が高いセルラインを分けてほしい」という手紙を書きました。すると、すぐにK562とYAC-1という細胞株を送っていただきました。これが、私のNK細胞研究の始まりです。そして、正常NK細胞に始まり、やがてNK細胞の腫瘍へと研究領域を広げながら、私のライフワークとなっていきました。
研究を進めていくと、NK細胞の活性はピシバニールの投与で上昇することが判りましたが、「がんを免疫でやっつけられないか」という可能性に魅力を感じていた私は、がんの中でも造血器腫瘍の臨床をしつつ、同時にNK細胞の研究も進めたいと考えるようになりました。
そこへ、すでに女子医大へ移っていた溝口秀昭先生から「女子医大に来て、血液内科の診療を一緒にやらないか」と声が掛かりました。そして1980年に女子医大に移り、血液学を学びつつ、診療と研究に没頭するようになりました。特に研究では、インターフェロンやIL-2などで活性化したキラー細胞やbispecific antibodyが、患者さんの白血病細胞やリンパ腫細胞をどうすれば効率良く殺すことができるのか、といったテーマに取り組みました。

〈後編では、NK腫瘍研究会の立ち上げ、そして、再びのアメリカ生活を経て、帰国後に道東・鶴居村で始めたリンパ腫研究会(Tsurui Lymphoma Workshop)についてお話しいただきました。〉