国立大初の「血液・腫瘍内科学」教授を22年
新生・血液学会の理事長として礎を築く(前編)
金倉譲(一般財団法人住友病院 顧問)
2019.05.16
「この人に聞く」のシリーズ第7回では、大阪大学血液・腫瘍内科教授を22年務め、2019年3月に退職された、住友病院顧問の金倉譲氏にご登場いただきます。内科医として臨床に携わろうと血液内科に進んだ金倉氏は、卒業後すぐに大学院に入学したことをきっかけに、研究の道に進み、43歳にして阪大教授に就任し、22年間教授を務めました。その間、2008年に日本血液学会と日本臨床血液学会が統合された後に理事長に就任し、現在の活気ある血液学会の基盤を築き上げました。「自分の殻に閉じこもらず、若い時代に研究、留学などたくさんのことに挑戦してほしい」と話します。
金倉譲(一般財団法人住友病院 顧問)
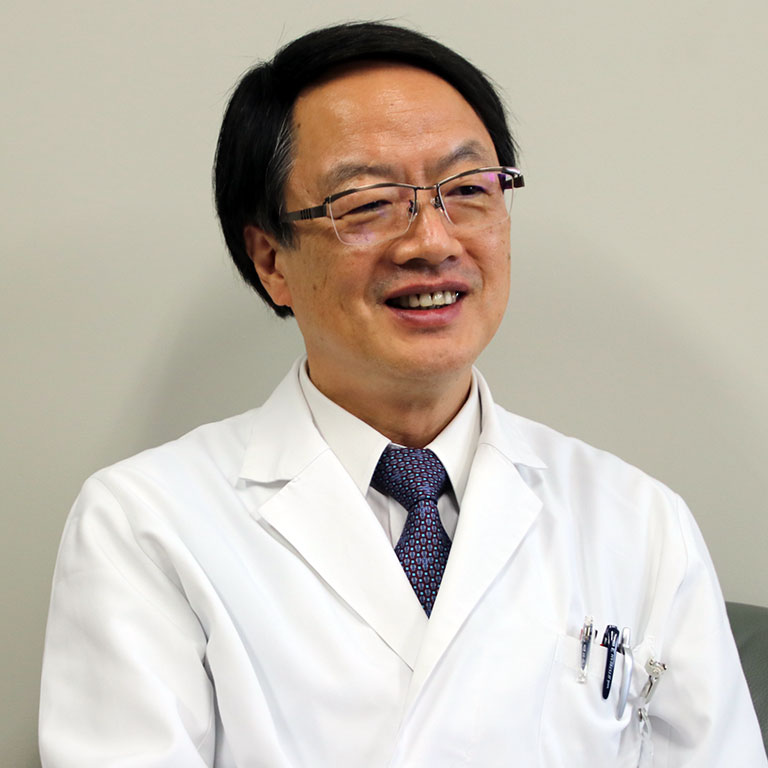
1979年大阪大学医学部卒業。同年4月より同大学大学院内科専攻へ。83年より大阪府立成人病センター第5内科勤務。85年大阪大学医学部癌研腫瘍代謝助手。88年7月より米国・ハーバード大学ダナ・ファーバー癌研究所 research associate。90年7月大阪大学第二内科助手。97年同大医学部血液・腫瘍内科教授に。2019年3月退職、4月より現職。2008年に日本血液学会と日本臨床血液学会が統合され、2009年新・日本血液学会の理事長に就任。
この3月で、卒業以来40年間ほぼ一貫して在籍、勤務した大阪大学を退職し、住友病院顧問に就任しました。国立大学初の「血液・腫瘍内科学」の教授に就任してから22年以上が経ちました。この間に多くの方にお世話になり、この場をお借りしてお礼を申し上げます。今後も、血液・腫瘍研究グループの一員として、血液内科医の職務を全うするつもりです。
良い臨床医を目指し血液内科へ進む
移植医療の転換点を目の当たりにする
私は四国・徳島の出身で、良い臨床医になろうと考えて大阪大学に進学しました。メスを握る外科医になる自信はなかったので、大学生のときに内科医になろうと決めました。
私が学生のころは、内科は第一内科、第二内科、第三内科に分かれていました。第一内科は優秀な人の集まる企業的な内科で、第三内科は研究者を養成する内科という印象でした。一方、第二内科はどちらかと言うと臨床を重視し、所属の先生方の人柄は穏やかと感じていました。ただ、当時第二内科教授だった垂井清一郎先生は、糖原病Ⅶ型(垂井病)の発見者で世界的に名前が知られており、「特殊から普遍へ」という考え方で臨床の研究も大事にしていました。患者さんを緻密に観察し、特殊な患者さんからでも普遍的な何かを得られるような研究をし、英語論文もどんどん書いていこうと話されていました。
学生時代の講義で、当時メジャーだった心臓や消化器ではなく、血液や神経の分野に興味を持ち、どちらかに進みたいと漠然と考えており、特に理路整然とした血液学が一番面白いと思っていました。そして私は垂井先生の姿勢に共感し、卒業後にすぐ大学院に進学し、第二内科グループの一つであった血液内科に進もうと決めました。当時は、大学院が“復活”した時代で、垂井先生はそこで研究者を育てたいと考えていたようです。第二内科には1学年で20〜30人が入局しており、大学院の定員はわずか2名。いわばエリート研究者の養成コースでした。
大学院では木谷照夫先生の指導のもと、研究を進めました。臨床にも興味があったのですが、「今はとにかく研究をした方がいい」と言われ、基礎講座に配属されたりもし、私の進路は予想外の方向に向き始めました。
1983年に大学院を修了、大阪府立成人病センターの第5内科の勤務となり、臨床医としての修練を始めました。当時、正岡徹先生らが取り組んでいた白血病に対する骨髄移植は「連戦連敗」でしたが、84年に21例目の患者さんがうまくいき、その後は亡くなる患者さんがほとんどいなくなりました。移植医療が転換する時代の幕開けを目の当たりにしました。

米国留学でチロシンリン酸化などを研究
43歳のとき“3段跳び”で助手から教授へ
85年に大阪大学に戻り、マスト細胞の研究で世界的に有名になっていた北村幸彦先生の講座の助手となり、3年間、基礎医学を学びました。マスト細胞を中心に研究をしていましたが、将来は臨床医として血液疾患の研究をしたいと考えていました。ちょうど、ハーバード大学や米国国立衛生研究所(NIH)と共同研究をしており、ハーバードの病理医のGalli先生の元を訪れた際に、そのことをお話ししたところ、何人かの血液領域の研究者を紹介してくれました。その一人がJ. Griffin先生でした。
Griffin先生に「留学したい」と伝え、日本に戻ってから改めて書状を送ったところ、「ぜひ来なさい」との返事があり、2年間、ダナ・ファーバー癌研究所のresearch associateとして研究に取り組みました。
テーマは、チロシンリン酸化などにおけるシグナル伝達でした。アカデミアの世界でトップを目指すという野望はありませんでしたが、当時のダナ・ファーバーには、イマチニブの開発につながる研究をしていたBrian Druker氏ら、気鋭の研究者がたくさんおり、多くの刺激を受けました。
90年に帰国し、第二内科助手になりました。帰国後、白血病細胞におけるc-kit遺伝子の機能解析を進め、93年には、c-kit遺伝子変異を持つ白血病細胞では、受容体型チロシンキナーゼ(KIT)が恒常的に活性化され、リン酸化が継続することを見出し、この研究結果は『J Clin Invest』誌に掲載されました。さらに、c-kit恒常的活性化変異がGIST(消化管間質腫瘍)のドライバー遺伝子であるという発見へと発展しました。これは98年の『Science』誌に掲載されました。これらの報告は、日本の血液疾患研究のプレゼンスを高めたと自負しています。
93年に大阪大学医学部と附属病院は大阪・中之島から吹田市に移転し、微生物病研究所附属病院と統合、国立大学では初めて「血液・腫瘍内科学」を標榜する科として大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科が設立されました。そして私は97年に助手から教授に就任しました。大学卒業後18年目、43歳のときです。それから22年間、教授職を務めることになりました。
研究グループを、リンパ球グループ、造血幹細胞グループ、赤血球グループ、血小板グループなどに分け、血液領域の様々な研究を行なえる体制を整えました。また、大阪大学には発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)の分子病態研究で世界的に評価されている木下タロウ先生がおられ、PNHの研究に定評があります。私自身は、赤血球系疾患の臨床や研究の経験はなかったのですが、先代教授の木谷照夫先生の後任としてPNH 研究を引き継ぎました。西村純一先生らが中心になってこの分野の研究を進め、PNH治療薬のエクリズマブ不応の原因として補体C5の遺伝子変異を発見し、これは『New England Journal of Medicine』誌に掲載されました。
副病院長、卒後教育開発センター長なども務め、臨床研修必修化、病院の診療科に沿って講座を臓器別に再編成するなどの業務にも汗を流しました。

〈後編では、日本血液学会と日本臨床血液学会が統合された後の新生・日本血液学会の理事長に就任したときのお話や現在の血液学についてのお考えをお聞きしました。〉